特徴
当科では、肺がん、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群など、幅広い疾患の診療を行っています。
臨床ではどのような疾患も診る必要があるため、全身を診る総合的な医療を心掛けています。
研究では肺がん、気道疾患、間質性肺疾患の3つの領域に重点を置き、各々の領域で突出した研究力を目指しています。

地域を守る呼吸器内科医
金沢大学附属病院は北陸の中心部に位置しており、金沢市のみならず、石川県、北陸地方の各地域から多くの患者さんが通院されています。 大学病院には最後の砦としての役割がありますので、診断困難例や治療困難例も多く紹介されます。
そのため、私たちは協働して診療を行うとともに、最良の医療が提供できるように努めています。また地域の基幹病院や関連病院の先生方とも協力しながら、北陸の地域医療を支えています。

リサーチマインドを持った
呼吸器内科医
研究できることが大学病院の魅力です。 私たちは先端的な研究手法・技術を用いて、新しい診断方法や治療薬の開発にも取り組む呼吸器内科を目指しています。 日常臨床で経験した疑問をもとに研究を行い、リサーチマインドを持った臨床医を目指すとともに、そこで得られえた成果を臨床に還元できるように努めています。
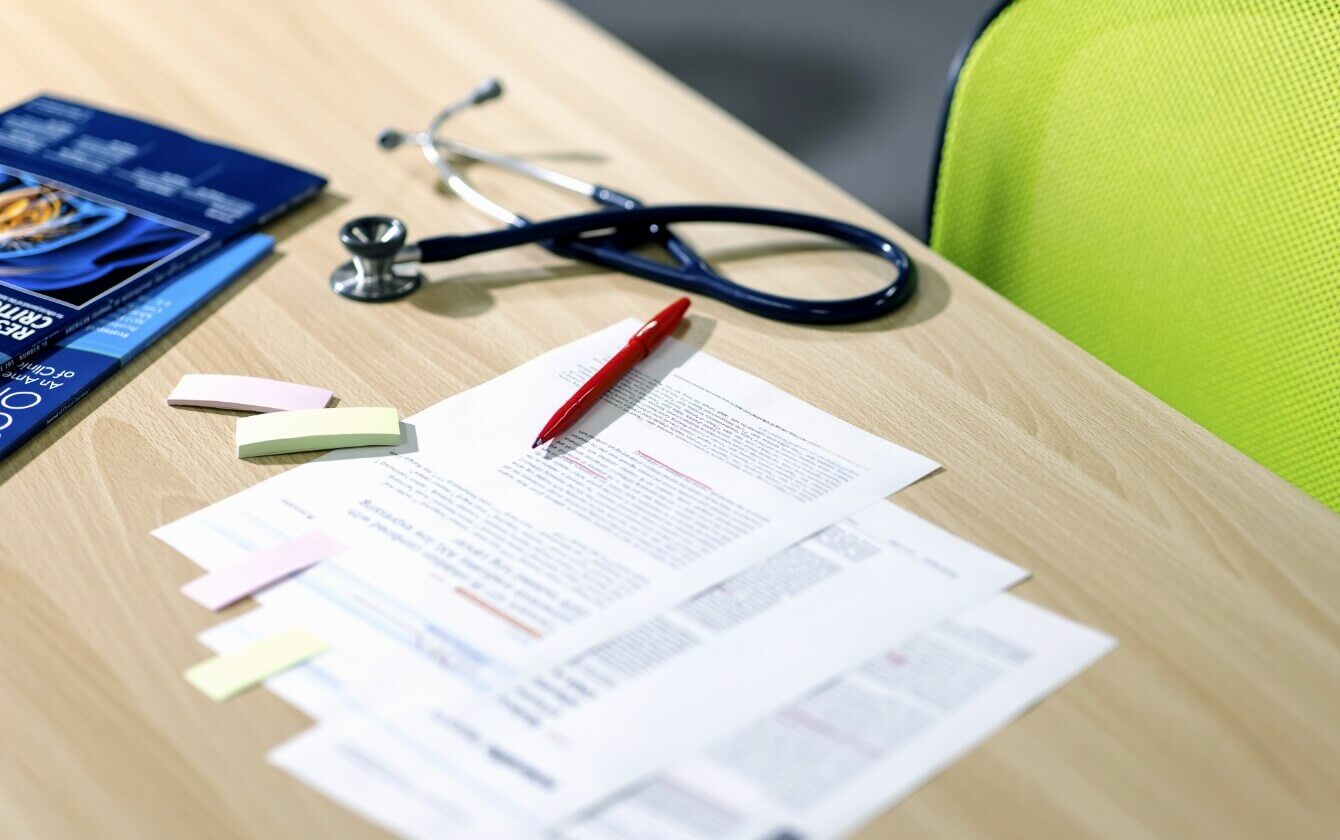
世界に発信する呼吸器内科医
私たちは、これまでも肺癌、間質性肺疾患、慢性咳嗽の分野で、世界に向けて新しい知見を発信し続けてきました。 新たに得られた知見を大学や北陸にとどめておくのではなく、世界に向けて発信します。 日常臨床で経験した小さな疑問を大切にし、どんなに些細なことでも世界に向けて発信し続ける呼吸器内科医を目指します。
臨床
肺がんは罹患数、死亡数ともに年々上昇しており、悪性腫瘍の中で死亡率第1位となっています。そのため迅速な診断と治療が必要です。胸部X線写真やCT検査で疑われた異常陰影に対し、超音波気管支鏡ガイド下針生検(EBUS-TBNA)やガイドシース併用気管支内超音波断層法(EBUS-GS)など、最新の気管支鏡検査法を用いて診断を行います。呼吸器内科では、主に進行肺癌に対して化学療法や放射線療法を行っています。
近年、肺がんにおける薬物療法の進歩は目覚ましいものがあります。腫瘍組織や血漿を用いてがんの遺伝子変異を調べ、各々の遺伝子異常に応じた分子標的薬で治療を行います。また、免疫チェックポイント阻害薬を中心とした新規薬剤の登場に伴い、進行肺癌と診断されても長期生存が得られる時代になりました。患者さんの価値観を大切にしながら、より良い治療を選択するよう努めています。また未来の標準治療の開発に貢献できるように、様々な国際共同臨床試験にも積極的に参加しています。
間質性肺疾患は、肺の間質に炎症や線維化がおこる疾患です。疾患の種類は多彩で、呼吸器疾患の中では診断が難しく、難病とされています。原因として自己免疫性、薬剤性、職業性、環境性、感染性、家族性などがありますが、多くは原因が特定できず「特発性間質性肺炎」に分類されます。私たちは、患者さんの職業歴や生活環境も含めた詳細な病歴、血液検査、画像検査、気管支鏡検査、胸腔鏡下肺生検の情報をもとに、診断と治療方針を決定します。そして定期的にカンファレンスを行い、各専門領域とも連携しながら、患者支援に取り組んでいます。
抗線維化薬の登場により治療の幅は広がりましたが、未だに診断・治療困難例が多いのが現状です。院内・院外からの紹介や、セカンドオピニオンによる相談も常時受け付けています。間質性肺炎の病態解明や治療の開発を進めるため、患者さんのご協力のもと、積極的に臨床研究や多施設共同研究を行っています。
咳嗽は最も頻度の高い受診動機(症状)の一つです。感染症、アレルギー疾患、肺がんなどあらゆる呼吸器疾患が咳嗽の原因となります。長引く咳嗽を診療する時、肺がんや間質性肺炎、肺結核など重篤となり得る呼吸器疾患をまず検索することから始まります。8週間以上持続する場合は慢性咳嗽と呼ばれ、その主な原因は咳喘息、アトピー咳嗽、副鼻腔気管支症候群、胃食道逆流症です。当科は長年、慢性咳嗽の診療に力を入れてきました。カプサイシンやメサコリンなどの薬剤負荷検査を導入し、多面的に評価しています。病態に基づいた診断と治療を行うとともに、難治性咳嗽の病態解明と治療の探索にも取り組んでいます。
気管支喘息は何らかの原因で気管支が狭くなり、喘鳴、呼吸困難、咳嗽を繰り返す病気です。日本では約1000万人の患者さんがいると言われています。小児だけでなく、成人や高齢者で初めて発症する場合もあるため、注意が必要な病気です。治療の第一選択は吸入ステロイド薬で、一般的に気管支拡張薬も併用されます。
吸入ステロイド薬の登場や吸入デバイスの改良により、喘息死は年々減少しています。一方、吸入薬のみでは改善しない「重症喘息」が今もなお存在します。当院はアレルギー専門医療機関であり、免疫反応を制御する『生物学的製剤』や、気管支鏡を用いて気道平滑筋を減少させる『気管支熱形成術』を積極的に行っています。
たばこの煙を主とする有害物質を長期間吸入することによって生じる、肺の生活習慣病です。肺胞の破壊による気腫化や末梢気道の線維化、肥厚および粘液分泌貯留による気道狭窄が起こり、徐々に息切れが進行します。治療の基本は禁煙で、そのための生活指導が非常に重要です。その他、気管支拡張薬やリハビリテーション、感染予防のためのワクチン接種、必要に応じて酸素療法を行います。私たちは、近隣の医療機関とも協力しながら、COPDの進行を抑え、予後を改善できるように努めています。
肺は外気を介してウイルスや細菌などの病原体にさらされており、呼吸器と感染症は切っても切り離せない関係です。人口の高齢化に伴い増加する肺炎、全世界にパンデミックを引き起こしている新型コロナウイルス感染症、免疫抑制薬や生物学的製剤の普及に伴い増加している日和見感染症など、呼吸器内科医の重要性は増してきています。私たちは、臨床症状や血液・画像・培養検査、時には気管支鏡を用いて、原因病原体を特定し、適切な治療を行っています。